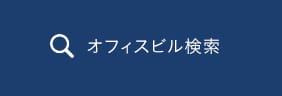「三井本館」重要文化財指定のお知らせ
平成10年10月14日 三井不動産株式会社
三井不動産株式会社(本社:東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 社長 岩沙弘道)は、当社が所有する「三井本館」(所在:中央区日本橋室町二丁目1番1号、地上7階、地下2階建、建築面積4,559m2)が、文化財保護審議会の答申(平成10年10月16日予定)を受け、複数の会社が入居する大規模なオフィスビルとして初めて、本年末に重要文化財の指定を受ける運びとなりましたのでお知らせいたします。
「三井本館」は、三井財閥を形成する三井合名会社、三井銀行(現さくら銀行)、三井信 託(現三井信託銀行)、三井物産、三井鉱山等の主要各社の本社が入る、いわば財閥の拠点的な機能を持つ建物として作られたもので、昭和4年3月に竣工し、竣工後69年を経て現在にいたっております。
「三井本館」は「国宝及び重要文化財指定基準」の「意匠的に優秀なもの」および「歴史的価値の高いもの」として評価をいただいており、意匠的評価としては「外壁を貫いてそびえるコリント式の列柱や1階の銀行・信託銀行の営業室のインテリアは、團琢磨のデザインポリシーをよく示すもので、建築作品としてみた場合に極めて優れている」とされています。また、歴史的評価としては「アメリカの技術を導入して建設された初期のオフィスビルディングとして、我が国の昭和初期を代表する建築物で現存する最古のアメリカンタイプのオフィスビル」と評されております。
当社といたしましては、重要文化財の指定の意義・重要性・影響等を十分に認識した上で、今後も同建物のオフィスビルとしての機能を保ちつつ、引き続き建物の価値の維持・保存に努めてまいりたいと考えています。
【三井本館の歴史について】
- 旧三井本館の建て替え
大正12年関東大震災により旧三井本館が罹災し、補修か建て替えかの議論があり、最終的に三井合名会社社長 三井八郎右衛門高棟,理事長 團琢磨により「建て替え」の決定がなされました。 - 「近代化されたアメリカの建築生産方式への期待と優秀な工業化製品の活用」を意図し下記に依頼
設計:トローブリッジ・アンド・リヴィングストン事務所(当時ニューヨーク三大建築事務所の一つ)
施工:ジェームス・スチュアート社(在ニューヨーク) - 團琢磨のデザインポリシー
「Grandeur(壮麗)、Dignity(品位)、Simplicity(簡素)」 - 総事業費
2,131万円(当時の一般的なビルの建築費は、3.3m2あたり200円程度でしたが、三井本館は約10倍の2,200円かかっております。) - 建築期間
地鎮祭 大正15年5月31日 上棟式 昭和2年11月10日 竣工 昭和4年3月23日 落成 昭和4年6月11日 落成式挙行 開館 昭和4年6月15日 開館式挙行 工事日数 964日(2年8ヶ月) 従業延人員 588,193人 - 規模
敷地面積 5,610m2 (約 1,700坪) 延床面積 31,660m2 (約 9,580坪) 建築様式 アメリカ型の古典主義建築
(アメリカンボザールのなかのクラシカルリヴァイバル)階数 地上7階、地下2階 主体構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨使用数量 9,600トン
(坪当たり約1トン、現在では0.3〜0.5トン)鉄筋使用数量 470トン 仕上げ 外装:茨城県稲田産花崗石積、東西南3面に合計22本の「コリンシャン」 丸柱を並列
内装:玄関・営業場は壁面柱とも全部イタリア産大理石を使用
特別室の高羽目、腰羽目は楢、胡桃、樺、桜、「マホガニー」、「チーク」を使用 - その他
- 三井本館は、三井合名会社のほか三井物産株式会社、三井鉱山株式会社、株式会社三井銀行(現株式会社さくら銀行)、三井信託株式会社(現三井信託銀行株式会社)などの三井財閥直系各社を収容するために建設されたもので、三井財閥にふさわしい豪華なビルの建設を目論んだものでありますが、その内容はむしろ控え目に公表されたため、学術的な側面での認知度は低かったようです。
- 三井銀行営業場金庫、および信託会社保護預庫の円形扉は「モスラー」社製で重量は50トンありますが、重量制限のため日本橋上を運ぶことを許可されず、新常盤橋際まで船で運び陸上げし、深夜、現場まで運びました。
- 平成元年6月に、三井本館が竣工後、60周年を迎えたのを記念して、記念誌「三井本館」を発刊いたしました。
- 平成2年9月に、東京都の「歴史的建造物の景観意匠保存事業」の第1号の補助をいただき、第二次世界大戦当時に金属の供出に協力して撤去した鎧戸(西・南・東の入り口に7ヶ所、14枚)を復元いたしました。
【「三井本館」についての文化庁作成資料】
三井本館 一棟
東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 三井不動産株式会社
指定基準
「(一)意匠的に優秀なもの」及び「(三)歴史的価値の高いもの」による。
説明
三井本館は、日本橋の北方、中央通りの西側にある街区の南に位置する。三井財閥を形成する三井合名会社、三井銀行、三井信託、三井物産、三井鉱山等の主要各社の本社が入る、いわば財閥の拠点的な機能を持つ建物としてつくられたもので、大正15年6月に工事着手、昭和4年3月に竣工、同年6月に開館した。
その建物は、前進の本館が関東大震災によって被害を受けたにともない行われたもので、工事はアメリカ・ニューヨークの各社に発注された。工事記録等から、設計管理はトローブリッジ・アンド・リヴィングストン(Trowbridge and Livingston)事務所、施工はジェームス・スチュワート(James Stewart)社で、構造設計ワイスコッフ・アンド・ピックワース(Weiskopf and Pickworth)事務所が担当したことが知られる。
東西と南の三方が道路に面した東西に長い形の建物で、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積4556.6平方メートル、地上5階地下2階建てで、屋上に塔屋を設ける。1階を中2階が2つ重なる吹き抜けの大空間とするため、実際には地上7階建の高さになっている。地階と1階は方形平面で、2階以上は、1階につくられた3箇所のガラス天井を囲う形の目の字形平面になる。
外部は、各部を花崗岩で仕上げ、道路に面した三方に1階と2階を通したコンクリート式の大オーダーの列柱(両脇2本が角柱で、その他はフルーティング付の円柱)を立てる点に特徴がある。3階の上部にコーニスを廻し列柱上のエンタブレチュア風に扱い、同階壁面に主要各社の業務内容を表現した浮き彫りを起き、4階のパラペットに連続した花形の彫刻を巡らす等、要所には華やかな装飾が用いられている。また、5階を4階以上よりわずかにセットバックして建て、重圧感を軽減させ安定感をもたせる等、全体の比例にも季が配られている。
内部は、1階が三井信託(現三井信託銀行)と三井銀行(現さくら銀行)の営業場等、2階から5階が三井銀行、三井合名、三井物産等の各社の事務室等にあてられている。地下は三井銀行・三井信託の倉庫及び機械室等で、地下1階には三井信託の保護預庫がつくられている。
1階の営業場は、吹き抜けの大空間で、床・柱・接客用のカウンター等各部の仕上げに大理石を用い、天井のプラスター下地にペンキ塗りで仕上げる。ドリス式の巨大な柱を何本も並べる一方、柱頭・天井・梁の縁等の要所に装飾を施す等、力強さの中に華やかさを感じさせる意匠となっている。場内は一連の空間となっているが、西側の3分の1ほどが三井信託、それ以外三井銀行で、両営業場の境には、装飾の付いた門構えをもった出入り口と低い間仕切り壁が設けられている。また、三井信託営業場には地下1階の保護預庫にいたる会談が中央に設けられている。
三井銀行営業場の西、1階西端部は2階以上の事務室への出入り口となる本館玄関があり、営業場とは壁で仕切られている。このため、三井信託の玄関、三井銀行の玄関、本館玄関がそれぞれ東、南、西の立面の中央に位置する構成となっており、全体の計画においても高い完成度をもっていることがうかがえる。
三井本館はアメリカン・ボザール・スタイルの建物で、その内外各部にみられる特徴は、三井合名会社理事長(当時)が揚げた壮麗(Grandeur)、品位(Dignity)、簡素(Simplicity)の3つの要素を具体化したという伝えをよく示している。また、大規模な中層建築物としては、アメリカの技術と生産システムを導入してつくられた最初期の例であり、歴史的な意義が認められる。複数の会社が入居する本格的業務用ビルとしても初期のもので、意匠的に優秀で完成度も高く、昭和初期を代表する建築物のひとつとして貴重である。
注)
- 本館建設の経緯等は「建築雑誌」1929年7月号及び「参考文献」による。
- トローブリッジ・アンド・リヴィングストン事務所はサミュエル・B・P・トローブリッジ(Samuel B.p. Trowbridge)とグッドヒュー・リヴィングストン(Goodhue Livingston)の共同事務所。主任技師のジョージ・W・ジャコピー(George W.Jacoby)が担当し、工事現場の管理は所員のリチャード・H・クック(Richard H.Cooke)と松田軍平が主に担当した。
ワイスコップ・アンド・ピックワース地味諸は、サミュエル・C・ワイスコップ(Samuel C. Weiskopf)とジョン・W・ピックワース(Jone W. Pickworth)の共同事務所。 - 部屋の利用方法や「保護預庫」の名称は注1文献による。
- 1階にある家具のうち、石造で床や壁に備え付けてあるもの(三井銀行営業場の接客用カウンター一式・出入り口カウンター2基・客溜机2脚・同椅子5脚、三井信託営業場のカウンター一式・出入り口机2脚・階段の腰壁廻り椅子4脚、本館玄関カウンター2脚)は指定範囲に含める。
- 【参考文献】による。三井合名会社理事長(当時)は、本館に関するこの3つの要素を英語で唱えており、その和訳も【参考文献】によった。
- 三井本気案の建設は、我が国の鉄骨鉄筋コンクリート造建築の歴史や工事化工法の歴史等の上で注目に値する。また、その工事によってコンクリート工事における大型ミキサーの使用等の機械化工法の徹底やセメント防水工法や防水シャッター工法等の様々な新工法の導入等がはかられたことが知られている。(【参考文献】による)
【参考文献】
- 三井本館記念誌編集委員会『三井本館』(三井不動産株式会社、1989年)
- 石田繁之助『三井本館と建築生産の近代化』(鹿島出版会、1988年)
【「三井本館」外観写真】

【内部(1階さくら銀行営業場部分)】