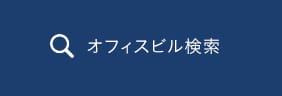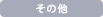【横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授監修 シニア世代の生活実態調査】
三井のシニアサービスレジデンス「パークウェルステイト」の住環境が交流・趣味・運動を後押し
“活発な生活習慣“が健康寿命延伸を促す可能性
2025年9月10日
三井不動産レジデンシャル株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:嘉村徹)は、三井のシニアサービスレジデンス パークウェルステイトの住環境が入居者の健康寿命へ与える影響を検証するため、全国6箇所のパークウェルステイト入居者とパークウェルステイトにお住まいでない全国の75歳以上シニア世代(以下、「一般シニア」)を対象に生活実態に関するアンケート調査を実施しました。
本調査の結果、パークウェルステイト入居者は、友人や趣味の数、交流頻度や運動習慣において一般シニアを上回り、日々の生活において活発な活動・交流を持っている傾向にあることが明らかとなりました。こうした背景には、パークウェルステイトの充実した共用部の存在や、多彩なサークル活動・イベントへの積極的な参加が大きく寄与していると考えられ、これらの生活習慣は、健康寿命の延伸にもつながる可能性が示されています。社会老年学の専門家で、高齢者の生活にかかわる様々な問題・課題の解決に取り組んでいる横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授による考察とあわせて、調査結果を公表いたします。
今後も、三井不動産レジデンシャルの全住宅事業のブランドコンセプトである「Life-styling × 経年優化」のもと、多様化するライフスタイルに応える商品・サービスを提供するとともに、安全・安心で快適にくらせる街づくりを推進し、持続可能な社会の実現・SDGsへ貢献してまいります。

調査レポートのポイント
- パークウェルステイト入居者、一般シニアを上回るアクティブな生活実態が判明
- 交流や活動習慣を促進するパークウェルステイトの住環境
- 横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授が解説
高齢者の孤独感軽減と健康寿命延伸に寄与するパークウェルステイトの価値
1.パークウェルステイト入居者、一般シニアを上回るアクティブな生活実態が判明
<本調査の背景・結果>
日本は急速に高齢化が進み、孤独死などの課題が深刻化しています。警視庁の発表によると、2024年に自宅で亡くなった一人暮らしの人は76,020人。そのうち65歳以上が58,044人(約76%)を占め、死後8日以上経過して発見されたケースは15,630人に上りました※1。
こうした中、三井不動産レジデンシャルのシニア向けサービスレジデンス「パークウェルステイト」は、2019年のパークウェルステイト浜田山を開業以来、全国で6レジデンスを展開。フィットネスやパーソナルトレーニング、多彩な「ディスカバリープログラム」などを通じて、入居者が健やかに、楽しく暮らせる仕組みを整えてきました。今回の調査は、これらの取り組みが入居者の生活や健康にどう役立っているかを検証し、高齢社会の課題解決の貢献に寄与しているのかを探ることを目的としています。
調査の結果、パークウェルステイト入居者は趣味や運動の参加率が一般シニアより高く、このような活発な活動はパークウェルステイトの住環境が後押ししていると考えられ、健康寿命の延伸に寄与する可能性が示されました。
趣味や運動は、生活を豊かにするだけでなく、将来の介護リスク低減や健康寿命の延伸にもつながることが研究で示されています。JAGES(日本老年学的評価研究)の調査※2によれば、趣味や運動の会に定期的に参加する高齢者は要支援・要介護認定リスクが最大24%低いことが確認されています。
(1)パークウェルステイト入居者は「友人の数」「交流頻度」「会話の長さ」が一般シニアを上回る結果
調査の結果、家族・親族以外の友人の数は、一般シニアが平均4.4人に対し、パークウェルステイト入居者は5.5人とより多いことがわかりました。
友人との交流頻度においても、パークウェルステイト入居者は突出しています。週に2回以上交流している人の割合は50%を超え、一般シニアの約30%と比べても圧倒的に高い結果となりました。
友人との会話時間においても、パークウェルステイト入居者は一般シニアを上回っています。パークウェルステイト入居者で1日の会話時間が「5分未満」と答えた人は10.3%に対し一般シニアは22.5%、一方で「30分以上」と回答した人は39.2%と、一般シニア(26.1%)の約1.5倍に上りました。こうした結果は、ダイニングや大浴場、フィットネスなど共用部を通じて自然に会話が生まれる環境によるものと考えられます。



(2)パークウェルステイト入居者は一般シニアに比べ趣味の数・ウォーキング回数が約1.3倍と際立つ結果に
趣味や運動の面でも、パークウェルステイト入居者は一般シニアを上回る活発さを示しました。友人との交流方法として「趣味のサークルや教室に参加する」と回答した割合は、一般シニアの33.6%に対し、パークウェルステイト入居者は47.8%と約1.5倍。内容も文化系から運動系、知的活動まで幅広く多彩でした。さらに趣味の数は、一般シニアが平均3.4個に対し、パークウェルステイト入居者は4.4個とより多い結果となりました。
また、健康を支える運動習慣についても、パークウェルステイト入居者は月平均9.7回と、一般シニアの7.6回を上回り、より高い運動意識を持っていることが示されました。



2.交流や活動習慣を促進するパークウェルステイトの住環境
こうした活発な暮らしを支えているのが、パークウェルステイトの住環境です。共用部やフィットネス、サークル・イベントなどを通じ、「健美」「喜楽」「活躍」をテーマに多彩なプログラムを展開しています。
- 毎日の生活を彩る大浴場やライブラリー、フィットネスルームのほか、交流が愉しめるカフェ等の充実した共用部
ラウンジや大浴場、ライブラリー、フィットネスなど充実した共用施設に加え、一部レジデンスにはクラブバーラウンジや入居者同士や地域との交流を育むカフェを備えています。 - ひと月当たり延べ4,000人以上が参加※3、独自開発の健康促進運動プログラム「健美体操」
「健美体操」の他にも椅子に座ったまま実施できる体操や、ヨガ等、体力や身体状況に応じて誰もが安心して参加できるプログラムがあり、運動を無理なく継続できることが大きな特長です。 - 75のサークル活動に延べ800人以上が参加※3、趣味や交流の機会が活発
活動内容は、麻雀・囲碁・将棋といった頭の体操から、絵画・コーラス・写経などの文化系、さらにビリヤード・社交ダンス・ゴルフといった運動系まで多岐にわたります。1つのサークルに20~30名が参加する例も多く、幅広い仲間づくりの場となっています。 - パークウェルステイト主催 毎月開催される多彩なイベントと入居者の活躍
各レジデンスでは、パークウェルステイトが主催する音楽コンサートや季節行事、映画鑑賞会、健康セミナーなど多彩なイベントを毎月開催しており、1回あたり数十人から100人超規模で多くの入居者が参加しています。

(1)共用部の例

(2)健美体操のイメージ

(3)サークル活動の例

(4)イベントの例
3.横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授による解説
高齢者の孤独感軽減と健康寿命延伸に寄与するパークウェルステイトの価値
今回の調査結果について、社会老年学の専門家で、高齢者の生活にかかわる様々な問題・課題の解決に取り組んでいる横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授に監修頂き、結果についての考察をいただきました。
■横浜国立大学・安藤孝敏名誉教授
専門分野:社会老年学、高齢者心理学、人と動物の関係学 イノベーションの視点から、近未来の超高齢社会のあり方を構想し、高齢者の生活に関わる多様な課題の解決に取り組んでいます。特に、普通に暮らしている高齢者の視点を重視した実証研究を推進するとともに、心の健康や社会参加を支える実践的な支援にも力を注いでいます。

<調査結果が示す、パークウェルステイトに入居するメリット>
高齢者の孤独感や健康状態は、交流の頻度や趣味の有無、住環境など、さまざまな要因によって左右されます。孤独を防ぎ、健康を維持するためには、社会的なつながりを持ち続けることが不可欠です。
三井不動産レジデンシャルが展開するシニアレジデンス「パークウェルステイト」は、シニア世代が安心・快適に、そして自分らしく暮らせるよう、良好な住環境と多様なサービスを提供しています。パークウェルステイトには、入居者が趣味や交流を楽しめるように、多彩な共用スペースが整備されており、自由参加型のアクティビティも充実しています。これらの活動を通じて、新しい仲間との交流が自然に生まれています。
調査結果ではパークウェルステイトの入居者は交流が活発で、「10人以上」友人がいると回答した方は一般シニアの約1.5倍、「週4回以上」友人と交流する人の割合は一般シニアに比べて約2.4倍でした。サークル活動やイベントなどを通じて新しい人間関係が築かれ、活発な交流が孤独感の軽減に大きく貢献していると考えられます。さらに、パークウェルステイトでは、ペットとの同居も可能です※4。ペットとの暮らしが精神的な安定や生活の張り、孤独感の軽減に寄与するという研究結果もあり、入居者にとって有益な環境です。
パークウェルステイトのように趣味や活動への参加を支援することで、孤独感の軽減、健康寿命の延伸につながる可能性があります。高齢者が安心して、豊かに暮らせるパークウェルステイトは、こうした支援を包括的に提供する場として、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。
<注釈>
- 1 令和6年中における警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者について 警視庁
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250401002.html - 2 井手一茂(千葉大学)種類別の社会参加頻度の介護予防効果は!? JAGES Press Release No: 376-23-8
https://www.jages.net/library/pressrelease/?
action=cabinet_action_main_download&block_id=5028
&room_id=549&cabinet_id=304&file_id=13553&upload_id=17535 - 3 2025年7月時点
- 4 ペット飼育にあたっては規約がございます。
【調査概要:三井不動産レジデンシャル 現役/シニア世代の生活実態調査】
| 調査対象者 | 一般シニア(75歳~96歳、平均81歳):400名 パークウェルステイト入居者(63歳~98歳、平均81歳):1,600名中370名回答 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット調査、アンケート調査 |
| 調査期間 | 2025年7月25日〜8月8日 |
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。
2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ&インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
三井不動産レジデンシャル「カーボンニュートラルデザイン推進計画」について
https://www.mfr.co.jp/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0315_01.pdf
すまいの高性能・高耐久化による省エネルギーの実現や、再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、ご入居後のくらしにおいても、楽しみながら省エネルギー行動等の環境貢献に取り組んでいただけるようなサービスの提供を推進し、すまいとくらしの両面からカーボンニュートラルの実現を目指していきます。
参考資料1
■「パークウェルステイト」について
当社グループの「シニアのためのサービスレジデンス」のブランドである「パークウェルステイト」は、運営面では、三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社が、お客様の生涯の暮らしに家族のように寄り添い続け、様々なサービス、サポートをしており、快適さと上質さに包まれた暮らしを実現する品格を備えた建物、充実した毎日のお食事やホームアテンダントサービス、生涯にわたる安心の介護・医療支援を提供しております。今後も「パークウェルステイト」ブランドのもと、三大都市圏をはじめとする大都市圏を中心に「シニアのためのサービスレジデンス」を積極的に展開してまいります。
パークウェルステイトについて詳しくはURLをご参照ください。 https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/
■レジデンス一覧
| 物件名 | 所在地 | URL |
|---|---|---|
| パークウェルステイト浜田山 | 東京都杉並区 | https://www.mfrw.co.jp/bukken/N1701/ |
| パークウェルステイト鴨川 | 千葉県鴨川市 | https://www.mfrw.co.jp/bukken/N1702/ |
| パークウェルステイト千里中央 | 大阪府豊中市 | https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/senri-chuo/ |
| パークウェルステイト西麻布 | 東京都港区 | https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/nishiazabu/ |
| パークウェルステイト幕張ベイパーク | 千葉県千葉市 | https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/makuhari/ |
| パークウェルステイト湘南藤沢SST | 神奈川県藤沢市 | https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/fujisawa/ |
■「健美」「喜楽」「活躍」をテーマに提供している多彩なプログラム
・「健美体操」等の運動プログラム
「体を動かす」「習慣化する」「交流が生まれる」という三位一体の仕組みが居住者同士のつながりを深める機会にもなり、健康維持と充実した生活の両面を支えています。
・自主運営のサークル活動
ご入居者の自主運営により展開、自主的で多様な活動が、日常的に人と関わる機会を生み出し、孤立感の少ない豊かな暮らしを後押ししています。

麻雀のイメージ
・パークウェルステイト主催の多彩なイベントと入居者の活躍
一部イベントでは入居者が講師として得意分野を生かし、他の入居者をサポートされるなど、互いに支え合いながら活躍いただく姿も見られます。

ひょうたんランプづくり

夏祭り
■ブランド初となるTVCMに吉永 小百合さんをブランドアンバサダーとして起用しております。

ブランド紹介ページ
https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/
CM特設サイト
https://www.mfrw.co.jp/parkwellstate/cm/
参考資料2
【安藤孝敏名誉教授による解説、孤独防止と健康を守る趣味・交流の重要性】
近年、日本では高齢化が進む中で、単身世帯や夫婦のみで暮らす高齢者の割合が増加しています。こうした生活スタイルの変化に伴い、高齢者が日常生活の中で感じる「孤独感」や、それが健康に及ぼす影響が重要な社会的課題として注目されています。内閣府が実施した調査によると、家族や友人との会話頻度が「ほとんど毎日」と答えた高齢者のうち、主観的健康状態が「良い」と感じている人の割合は90.1%に達しています。これは、日常的なコミュニケーションが心身の健康に良い影響を与えていることを示唆しています。一方で、「ほとんど会話をしない」と答えた高齢者では、「健康状態が良くない」と感じている人の割合が13.1%と高く、交流の少なさが健康面にネガティブな影響を及ぼしている可能性があることが分かります※5。
また、趣味や社会活動への参加も健康状態に大きく影響します。趣味を持つ高齢者は認知症の発症リスクが低く※6・7、社会活動に積極的な人ほど健康寿命が長くなる傾向があること※8が示されています。特に、JAGES(日本老年学的評価研究)による長期追跡調査では、同居家族以外との交流が週1回未満の高齢者は、要介護状態や認知症、死亡リスクが高まることが示されています。今回の調査からも分析できるように、趣味や交流は単なる娯楽ではなく、健康維持のための「予防的介入」として機能することを示しています。高齢者が自分らしく、安心して暮らすためには、趣味や交流の機会を積極的に持ち続けることが不可欠であり、それを支える仕組みを整えることが求められています。
<注釈>
- 5人との交流と健康長寿との関連 | 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tyojyu-shakai/hitotonokoryu-kenkochoju.html - 6 高齢者の趣味の種類および数と認知症発症:JAGES 6年縦断研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/67/11/67_19-046/_article/-char/ja - 7 趣味と要介護認知症との関連について|多目的コホート研究 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト
https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8955.html - 8社会参加と健康寿命との関連:大崎コホート 2006 研究
https://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/archive/publication/pdf/2020/2020_8.pdf
■孤独や健康状態を改善するために必要なポイント
孤独感や健康状態の悪化は、生活の質を著しく低下させる要因です。これらを予防・改善するためには、以下のような多面的かつ継続的な支援が必要です。
- 定期的な交流の場の提供
地域のコミュニティセンター、老人クラブ、自治会などが主催する趣味活動や運動教室は、高齢者が自然な形で人と関わる機会を得るための重要な場です。例えば、週に1回の体操教室や月に数回の囲碁・将棋クラブなどは、身体機能の維持だけでなく、参加者同士の会話や笑顔を生むことで、孤独感の軽減に寄与します。 - 地域とのつながりの強化
近所づきあいや地域イベントへの参加は、日常的な交流を促進し、孤立を防ぐ重要な要素です。例えば、町内会の夏祭りや防災訓練、地域カフェなどは、世代を超えた交流の場となり、高齢者が地域の一員として関わる機会を提供します。また、自治体やNPOによる訪問支援や見守り活動は、孤独感の軽減に効果的です。定期的な訪問や電話による安否確認は、安心感を与えるだけでなく、緊急時の対応にもつながります。 - テクノロジーの活用
スマートフォンやタブレット、ビデオ通話アプリ(Zoom、LINEなど)を活用することで、遠方の家族や友人との交流が可能になります。特に移動が困難な高齢者にとって、ICTは孤独感を軽減する有効な手段です。デジタルデバイドの解消に向けたICT講習会の開催も有効です。 - 精神的ケアの充実
高齢者は、加齢に伴う身体的変化だけでなく、配偶者の死、友人の喪失、退職・引退による社会的役割の喪失など、さまざまな精神的課題に直面します。カウンセリングやメンタルヘルス支援を通じて、心のケアを行うことも重要です。 - ペットとの共生
ペットとの暮らしは、高齢者にとって精神的な安定や生活の張りをもたらす大きな要素です。犬や猫などの動物は、無条件の愛情を提供し、日々の世話を通じて飼い主の生活に目的とリズムを与えてくれます。特に一人暮らしの高齢者にとっては、ペットが「家族のような存在」となり、孤独感を和らげる効果があります。近年では、ペット共生型の高齢者施設や、アニマルセラピーを取り入れた福祉サービスも増えており、動物とのふれあいが認知症予防やうつ症状の緩和に効果があることも報告されています。